2013年04月16日
脳は自分を活かすと他人が活きるつくり
本当の自分って何だろう?と
悩むときがあります。
何かに一生懸命なときは気づきませんが、
達成したときに、ふっと頭に浮かびます。
もっと違う自分がいるのかも。
自分ってもっと面白い人だったはず。
などなど、混乱したり大切なことにきづいたり。
ヒトは、自分自身のことが一番わからないわけですが、
ときにわかった!となったときは、
大きな喜びを感じます。
そもそも、
自分とは何でしょう?
そのヒントとして、自分とはどのような行動をしているか、
という表現系で見てみます。
自分の行動は、記憶の痕跡で決まります。
ヒトは、記憶をもとにしないと行動できません。
全く新しい行動でも、数%の記憶から要素をかき集めて
構成されています。
記憶の痕跡は3種類に分かれます。
①意識しながら行うもの
②行ってはいるけど他に意識が向いているもの
③最初から無意識なもの
どれが呼び出されるか、
特に③が呼び出されるには、
扁桃体(へんとうたい)という感情をつかさどる場所が
カギを握っています。
人と会って、強く感情が動かされると、
扁桃体からの経路が活性化し、
適切な痕跡を呼び出します。
そのときに、いつもと違う行動をとることがあります。
扁桃体が刺激される感情は、
快感のものもあれば不快感もあります。
不快感によって自分の行動がつくられていくと、
いつのまにか今の不快感を避ける、もしくは不快感を表現することが
普段の行動パターンになってしまい、
それが「私」になってしまいます。
これは誰もが望まないことですが、
そうなっていることには自分では気づけない。
今の自分が置かれている状況にいる人たち。
この人たちが私をつくっています。
こう考えてみると、
その人たちから快の部分を発見して、
そこから自分の行動がつくられるように仕組みたくなります。
人の良いところを発見するというのは
難しいことですが、
自分の脳をうまい方向に機能させるためにも
必要だということが分かると、
妙に合点がいくこともあると思います。
自分自身をしっかり活かそうとすることは、
実は他人を活かすことにつながるように
脳はできているのかもしれません。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
今までの臨床経験をもとに執筆した本ですが、
みなさんからたくさんの反響をいただいております。
おかげさまで、5万部になりました。
ちょっとした行動が、毎日の生活を大きく変えていく。
そんな人間の仕組みが、
みなさんの充実につながっていけばうれしいです。
悩むときがあります。
何かに一生懸命なときは気づきませんが、
達成したときに、ふっと頭に浮かびます。
もっと違う自分がいるのかも。
自分ってもっと面白い人だったはず。
などなど、混乱したり大切なことにきづいたり。
ヒトは、自分自身のことが一番わからないわけですが、
ときにわかった!となったときは、
大きな喜びを感じます。
そもそも、
自分とは何でしょう?
そのヒントとして、自分とはどのような行動をしているか、
という表現系で見てみます。
自分の行動は、記憶の痕跡で決まります。
ヒトは、記憶をもとにしないと行動できません。
全く新しい行動でも、数%の記憶から要素をかき集めて
構成されています。
記憶の痕跡は3種類に分かれます。
①意識しながら行うもの
②行ってはいるけど他に意識が向いているもの
③最初から無意識なもの
どれが呼び出されるか、
特に③が呼び出されるには、
扁桃体(へんとうたい)という感情をつかさどる場所が
カギを握っています。
人と会って、強く感情が動かされると、
扁桃体からの経路が活性化し、
適切な痕跡を呼び出します。
そのときに、いつもと違う行動をとることがあります。
扁桃体が刺激される感情は、
快感のものもあれば不快感もあります。
不快感によって自分の行動がつくられていくと、
いつのまにか今の不快感を避ける、もしくは不快感を表現することが
普段の行動パターンになってしまい、
それが「私」になってしまいます。
これは誰もが望まないことですが、
そうなっていることには自分では気づけない。
今の自分が置かれている状況にいる人たち。
この人たちが私をつくっています。
こう考えてみると、
その人たちから快の部分を発見して、
そこから自分の行動がつくられるように仕組みたくなります。
人の良いところを発見するというのは
難しいことですが、
自分の脳をうまい方向に機能させるためにも
必要だということが分かると、
妙に合点がいくこともあると思います。
自分自身をしっかり活かそうとすることは、
実は他人を活かすことにつながるように
脳はできているのかもしれません。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
今までの臨床経験をもとに執筆した本ですが、
みなさんからたくさんの反響をいただいております。
おかげさまで、5万部になりました。
ちょっとした行動が、毎日の生活を大きく変えていく。
そんな人間の仕組みが、
みなさんの充実につながっていけばうれしいです。
Posted by ActiveSleep at
08:45
│Comments(0)
2013年04月15日
かゆみで悩んだら朝はまず着替えて
朝起きたとき、
「おはよー」と言いながら
首元や胸元をポリポリと掻いている場面、
よく見かけます。
何気ないシーンですが、
体のかゆみで悩む方には
見逃せないチャンスです。
かゆいときは
朝、起きたらすぐに着替えてみましょう。
睡眠中は、
汗で老廃物を排出します。
一晩中の汗を吸い取った朝のパジャマは
雑菌でいっぱいです。
ヒトは、
朝と眠る前の時間帯に、
ヒスタミンという物質が増えます。
ヒスタミンは、炎症の介在として働き、
体がかゆくなる。
そういえば、眠る前と起きがけに
お尻の上やわき腹、わきの後ろがかゆく
なりますよね。
朝は、パジャマのままのんびりと
飲み物を飲みながら新聞でも
読みたいところですが、
この時間に、皮膚にずっと雑菌をつけていることに
なるので、防御反応としてのかゆみも
強くなってしまいます。
朝は、まず着替えてしまえば
皮膚に無用な刺激を与えることがありません。
夜、着替えずに洋服のまま眠ってしまうのも同じ。
一人暮らしだと自由になっていちいち着替えるのが
面倒になったりしますが、
かゆみ止めを常時使っているのなら、
ここは頑張りたいところです。
ちょっとしたことですが、
自分で原因をつくってしまって、
その対処に追われ始めるとなかなか抜け出せなく
なってしまいます。
起きたら着替える。
ぜひ、意識してみてください。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
頭痛やかゆみ、胃もたれや下痢。
別に病院にいくほどでもないし、
会社を休むほどでもないけど抱えている悩み。
大したことなければ、体質だとあきらめてしまいがち。
睡眠は、昼間の脳と体を
しっかり活動できるように先手を打って
準備する活動です。
この本では、
「起床から4時間以内に光を見て、
6時間後に目を閉じ、
11時間後に姿勢を良くする」という
4-6-11の法則で、
睡眠のリズムを整える科学的な方法をご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひ、ご活用ください。
「おはよー」と言いながら
首元や胸元をポリポリと掻いている場面、
よく見かけます。
何気ないシーンですが、
体のかゆみで悩む方には
見逃せないチャンスです。
かゆいときは
朝、起きたらすぐに着替えてみましょう。
睡眠中は、
汗で老廃物を排出します。
一晩中の汗を吸い取った朝のパジャマは
雑菌でいっぱいです。
ヒトは、
朝と眠る前の時間帯に、
ヒスタミンという物質が増えます。
ヒスタミンは、炎症の介在として働き、
体がかゆくなる。
そういえば、眠る前と起きがけに
お尻の上やわき腹、わきの後ろがかゆく
なりますよね。
朝は、パジャマのままのんびりと
飲み物を飲みながら新聞でも
読みたいところですが、
この時間に、皮膚にずっと雑菌をつけていることに
なるので、防御反応としてのかゆみも
強くなってしまいます。
朝は、まず着替えてしまえば
皮膚に無用な刺激を与えることがありません。
夜、着替えずに洋服のまま眠ってしまうのも同じ。
一人暮らしだと自由になっていちいち着替えるのが
面倒になったりしますが、
かゆみ止めを常時使っているのなら、
ここは頑張りたいところです。
ちょっとしたことですが、
自分で原因をつくってしまって、
その対処に追われ始めるとなかなか抜け出せなく
なってしまいます。
起きたら着替える。
ぜひ、意識してみてください。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
頭痛やかゆみ、胃もたれや下痢。
別に病院にいくほどでもないし、
会社を休むほどでもないけど抱えている悩み。
大したことなければ、体質だとあきらめてしまいがち。
睡眠は、昼間の脳と体を
しっかり活動できるように先手を打って
準備する活動です。
この本では、
「起床から4時間以内に光を見て、
6時間後に目を閉じ、
11時間後に姿勢を良くする」という
4-6-11の法則で、
睡眠のリズムを整える科学的な方法をご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひ、ご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
08:12
│Comments(0)
2013年04月13日
休日昼のだるーい睡眠慣性
今週は、1~2時間おきに10分程度の短時間睡眠をとり、
4時前後2~3時間の睡眠をとる方法を週3日実施の、
半分やむなく半分実験でした。
睡眠不足状態で仮眠をとると
目覚めたときにだーるい感じになります。
これが睡眠慣性(sleep inertia)です。
慣性の法則の慣性なので、
文字通り睡眠を持ち越す感じです。
今日の昼は、この睡眠慣性を存分に味わいました。
仮眠した後、とにかく手足に力が入らない。
手も握れない。体はもちろん起こせない。
「力が入らないなぁ」と思っているとまた眠っている。
こんな状態を5回程度繰り返し、
ようやく手にじわーっとしただる気持ちいいみたいな
感じが出てきて頭を挙げられ、で、また眠る。
次にやっと目覚めて体を起こしてから、
ボーっとしてまだ手足は動かず。
家族との会話もあやふやだったものが
徐々に反応できるようになって、
ここで大きく背伸び。
「あースッキリしたー。良く寝たー」というところで、
最初の目覚めから30分過ぎて無事終了。
休日のだらーっと眠るのが気持ちが良いというのは、
この睡眠慣性を指していると思います。
ほんと、この無気力で力が抜けた感覚は、
いいですよね。
臨床的には睡眠慣性は睡眠不足の徴候として扱われ、
コンスタントに仮眠をとることで減っていくのですが、
全然なくなるのも、なんかつまらないですよね。
今日はしっかり満喫しました。
よかったよかった。
4時前後2~3時間の睡眠をとる方法を週3日実施の、
半分やむなく半分実験でした。
睡眠不足状態で仮眠をとると
目覚めたときにだーるい感じになります。
これが睡眠慣性(sleep inertia)です。
慣性の法則の慣性なので、
文字通り睡眠を持ち越す感じです。
今日の昼は、この睡眠慣性を存分に味わいました。
仮眠した後、とにかく手足に力が入らない。
手も握れない。体はもちろん起こせない。
「力が入らないなぁ」と思っているとまた眠っている。
こんな状態を5回程度繰り返し、
ようやく手にじわーっとしただる気持ちいいみたいな
感じが出てきて頭を挙げられ、で、また眠る。
次にやっと目覚めて体を起こしてから、
ボーっとしてまだ手足は動かず。
家族との会話もあやふやだったものが
徐々に反応できるようになって、
ここで大きく背伸び。
「あースッキリしたー。良く寝たー」というところで、
最初の目覚めから30分過ぎて無事終了。
休日のだらーっと眠るのが気持ちが良いというのは、
この睡眠慣性を指していると思います。
ほんと、この無気力で力が抜けた感覚は、
いいですよね。
臨床的には睡眠慣性は睡眠不足の徴候として扱われ、
コンスタントに仮眠をとることで減っていくのですが、
全然なくなるのも、なんかつまらないですよね。
今日はしっかり満喫しました。
よかったよかった。
Posted by ActiveSleep at
22:10
│Comments(0)
2013年04月12日
ELLE On lineで悩んだときに手にとりたい本をご紹介
なんだかうまくいかないな…と思ったときに
本を読んで救われることも多々あります。
自分の漠然としたもやもや感に
ピタッと当てはまる
言葉や写真、絵を見たときに、
脳は「わかった!」となってスッキリします。
脳が分かるには4つのパターンがあります。
①直観的にわかる
②まとまってわかる
③ルールを発見してわかる
④置き換えてわかる
本を読んでスッキリするのは
④の置き換えてわかる作用です。
脳が作り出す情報のかたまりである「こころ」は
常にある像として満たされていますが、
一つの像だけでは「わかる」という作用は生まれません。
新しく手に入れた他の像に置き換えてみて比較することで、
その関係性から「わかった!」と
新しい意味を生み出すことができます。
ELLE On line
「悩んだときに手にとりたい1冊」
http://www.elle.co.jp/wellness/trend/happy-spring_book_13_0411
では、私からも2冊ご紹介させていただいてます。
私は1番と11番。
すでにご存じ方も多い写真集と絵本ですが、
きっと深いところにピタッとくる感じがあると思います。
よしもとばななさんのご推薦本もありますよ。
ぜひ、ご覧ください。
本を読んで救われることも多々あります。
自分の漠然としたもやもや感に
ピタッと当てはまる
言葉や写真、絵を見たときに、
脳は「わかった!」となってスッキリします。
脳が分かるには4つのパターンがあります。
①直観的にわかる
②まとまってわかる
③ルールを発見してわかる
④置き換えてわかる
本を読んでスッキリするのは
④の置き換えてわかる作用です。
脳が作り出す情報のかたまりである「こころ」は
常にある像として満たされていますが、
一つの像だけでは「わかる」という作用は生まれません。
新しく手に入れた他の像に置き換えてみて比較することで、
その関係性から「わかった!」と
新しい意味を生み出すことができます。
ELLE On line
「悩んだときに手にとりたい1冊」
http://www.elle.co.jp/wellness/trend/happy-spring_book_13_0411
では、私からも2冊ご紹介させていただいてます。
私は1番と11番。
すでにご存じ方も多い写真集と絵本ですが、
きっと深いところにピタッとくる感じがあると思います。
よしもとばななさんのご推薦本もありますよ。
ぜひ、ご覧ください。
Posted by ActiveSleep at
09:08
│Comments(0)
2013年04月11日
TVつけて食事すると脳が働かない!?
仕事や子育てで忙しいときは
複数のことを同時進行させるマルチタスクです。
これは
脳のリハビリテーションという観点ではもっとも負担がかかる状況。
狙った能力を伸ばすことができないので、
なるべく避けるように注意します。
これは、
私たちの日常でも同じです。
マルチタスクはもっとも脳に負担をかける。
ただ、仕事、子育て、家事をそれぞれこなしていれば、
マルチタスクでない時間なんてありません。
常にフル稼働。
いやいや、
問題なのは暇な時間に何をしているかです。
暇なはずなのに、
TVをつけながら食事、
会話をしながらスマホなど、
自覚なくマルチタスクの状況をつくってしまって
いませんか?
自分はリラックスしているつもりでも、
脳の中に入ってくる情報はたくさん。
情報処理に追われていることには
変わりありません。
マルチタスクのようなたくさんの
エネルギーを要することは、
ここぞ!という肝心な場面にとっておきたいものです。
無駄に脳を消耗させてしまうことで、
疲れてしまっているのに、
その疲れは、仕事や子育てのせいだと思ってしまいがち。
無駄な消耗を防ぐには、
日常行為をシングルタスクにしてみましょう。
洗濯物を畳んでいるときは、TVや音楽を消す、とか。
雑音がいっぱい入ってくるからイヤホンで音楽を聴くことで
タスクを減らすという使い方もできます。
これは通勤中などに実践されている方も
多いのではないでしょうか。
自分の脳に入ってくる情報を制御すること。
これは、脳の働きを維持するためには
重要なことですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
脳内の情報量が自覚なく増えてしまうと、
睡眠中の情報処理作業にも負担がかかります。
寝つきのよさと朝のすっきり感をつくるためにも、
大事なときに大事な情報を処理できる脳を
つくっていきいましょう。
複数のことを同時進行させるマルチタスクです。
これは
脳のリハビリテーションという観点ではもっとも負担がかかる状況。
狙った能力を伸ばすことができないので、
なるべく避けるように注意します。
これは、
私たちの日常でも同じです。
マルチタスクはもっとも脳に負担をかける。
ただ、仕事、子育て、家事をそれぞれこなしていれば、
マルチタスクでない時間なんてありません。
常にフル稼働。
いやいや、
問題なのは暇な時間に何をしているかです。
暇なはずなのに、
TVをつけながら食事、
会話をしながらスマホなど、
自覚なくマルチタスクの状況をつくってしまって
いませんか?
自分はリラックスしているつもりでも、
脳の中に入ってくる情報はたくさん。
情報処理に追われていることには
変わりありません。
マルチタスクのようなたくさんの
エネルギーを要することは、
ここぞ!という肝心な場面にとっておきたいものです。
無駄に脳を消耗させてしまうことで、
疲れてしまっているのに、
その疲れは、仕事や子育てのせいだと思ってしまいがち。
無駄な消耗を防ぐには、
日常行為をシングルタスクにしてみましょう。
洗濯物を畳んでいるときは、TVや音楽を消す、とか。
雑音がいっぱい入ってくるからイヤホンで音楽を聴くことで
タスクを減らすという使い方もできます。
これは通勤中などに実践されている方も
多いのではないでしょうか。
自分の脳に入ってくる情報を制御すること。
これは、脳の働きを維持するためには
重要なことですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
脳内の情報量が自覚なく増えてしまうと、
睡眠中の情報処理作業にも負担がかかります。
寝つきのよさと朝のすっきり感をつくるためにも、
大事なときに大事な情報を処理できる脳を
つくっていきいましょう。
Posted by ActiveSleep at
08:13
│Comments(0)
2013年04月10日
脳の目覚まし時計を使う
目覚ましでジリジリ起きるのは
強制覚醒と呼びます。
とても不愉快ですね。
一方で
脳の目覚ましを使う
自己覚醒法という方法があります。
これは病院で指導される方法です。
睡眠の後半は実は起床準備期間です。
脳は、目覚める時間を頭の中で唱えると
起床できる体をつくるアドレノコルチコトロピンが
起床3時間前から分泌されて
バッチリ準備することができます。
この方法は、脳のシステムを活用するので、
訓練が必要です。
とはいっても、毎晩眠る前に
「6時に起きる」と唱えるだけですが。
運動会や文化祭のときに限って、
子どもはピタッと起きてきますよね。
何時に起きるということが脳内の言語を使って
プログラムできれば効果が発揮されます。
でも、これは
なにも行事のときに限って行わなくたって
いつもやったらいいんじゃない?
ということで、毎晩やれば
どんどんシステムの精度は高まります。
以前、マスコミの方を対象に研修でこの方法を話したら、
経験的にみんなやっていました。
短い時間で確実に起きるには
有効な方法だということは、必要な業種の人は
知っているのですね。
実行するときは、
最初は早く目覚め過ぎます。
ですが続けていくと
目覚ましより前に目覚められる。
脳のシステムを鍛えて朝スッキリ!
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
私たちの脳には使える資源が結構あります。
この本ではそんな資源をフル活用して
毎日の生活を充実させていく、
誰でもできる簡単なことをご紹介しています。
ぜひ、ご活用ください。
強制覚醒と呼びます。
とても不愉快ですね。
一方で
脳の目覚ましを使う
自己覚醒法という方法があります。
これは病院で指導される方法です。
睡眠の後半は実は起床準備期間です。
脳は、目覚める時間を頭の中で唱えると
起床できる体をつくるアドレノコルチコトロピンが
起床3時間前から分泌されて
バッチリ準備することができます。
この方法は、脳のシステムを活用するので、
訓練が必要です。
とはいっても、毎晩眠る前に
「6時に起きる」と唱えるだけですが。
運動会や文化祭のときに限って、
子どもはピタッと起きてきますよね。
何時に起きるということが脳内の言語を使って
プログラムできれば効果が発揮されます。
でも、これは
なにも行事のときに限って行わなくたって
いつもやったらいいんじゃない?
ということで、毎晩やれば
どんどんシステムの精度は高まります。
以前、マスコミの方を対象に研修でこの方法を話したら、
経験的にみんなやっていました。
短い時間で確実に起きるには
有効な方法だということは、必要な業種の人は
知っているのですね。
実行するときは、
最初は早く目覚め過ぎます。
ですが続けていくと
目覚ましより前に目覚められる。
脳のシステムを鍛えて朝スッキリ!
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
私たちの脳には使える資源が結構あります。
この本ではそんな資源をフル活用して
毎日の生活を充実させていく、
誰でもできる簡単なことをご紹介しています。
ぜひ、ご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
08:24
│Comments(0)
2013年04月09日
照明選びを間違うと子どもが不眠に!?
夜明るい中にいると、
脳を眠らせるメラトニンが抑制されてしまい
なかなk眠れません。
でもこれは、寝室の問題だけでは
ありません。
蛍光灯のリビングで3時間過ごすと
夜になれば出てくるはずの
メラトニン量は50%も減ってしまいます。
さらに、同じ環境に過ごしていても、
親より子どもの方が影響が強い。
子どもの方が光の感受性が強いので、
明るくすると簡単に眠れなくなってしまいます。
目には、明るさになれる現象があります。
一旦必要な明かりを消してみて、
しばらく過ごしてみます。
暗いとは言ってもそこそこ明るいので、
日常生活をおくるには別段不便はありません。
その後、もとの明かりに戻してみます。
すると
「まぶしい!」
こんな強い光にいつもあたっていたのかと
びっくりしてしまいます。
子どもがなかなか眠ってくれないのは、
親にとってはとってもストレス。
ぐずぐずしながら粘る子どもをなんとか寝かせようと
頑張った挙句に一緒に眠ってしまって、
自分の時間が全然ない!なんてことも多いはずです。
でもこれって、
冷静に考えてみると、その照明を選んだのは自分。
「早く寝なさい!」って言ってもそりゃ無理か・・・。
照明の色を変えてみましょう。
メラトニンは青色に近い照明で強く減ってしまう
特徴があります。逆に赤色に近い照明では
影響が少ない。
蛍光灯では、昼光色、昼白色が青色に近い照明で
電球色が赤色に近い照明です。
色を変えて、必要ない場所の照明は消し、
部屋全体を明るくしないように心がけてみるだけで、
子どもの脳の発達は随分促進されるはず。
知っていれば済む話です。
子どもの脳の成長のためにも、
お部屋の照明、見直してみませんか?
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
睡眠の悩みは尽きないですが、
日常のちょっとした工夫が突破口になることがあります。
この本では、誰でも今日から簡単にできる
科学的な睡眠の作り方を詳しくご説明しています。
毎日の生活の充実に、
ぜひご活用ください。
脳を眠らせるメラトニンが抑制されてしまい
なかなk眠れません。
でもこれは、寝室の問題だけでは
ありません。
蛍光灯のリビングで3時間過ごすと
夜になれば出てくるはずの
メラトニン量は50%も減ってしまいます。
さらに、同じ環境に過ごしていても、
親より子どもの方が影響が強い。
子どもの方が光の感受性が強いので、
明るくすると簡単に眠れなくなってしまいます。
目には、明るさになれる現象があります。
一旦必要な明かりを消してみて、
しばらく過ごしてみます。
暗いとは言ってもそこそこ明るいので、
日常生活をおくるには別段不便はありません。
その後、もとの明かりに戻してみます。
すると
「まぶしい!」
こんな強い光にいつもあたっていたのかと
びっくりしてしまいます。
子どもがなかなか眠ってくれないのは、
親にとってはとってもストレス。
ぐずぐずしながら粘る子どもをなんとか寝かせようと
頑張った挙句に一緒に眠ってしまって、
自分の時間が全然ない!なんてことも多いはずです。
でもこれって、
冷静に考えてみると、その照明を選んだのは自分。
「早く寝なさい!」って言ってもそりゃ無理か・・・。
照明の色を変えてみましょう。
メラトニンは青色に近い照明で強く減ってしまう
特徴があります。逆に赤色に近い照明では
影響が少ない。
蛍光灯では、昼光色、昼白色が青色に近い照明で
電球色が赤色に近い照明です。
色を変えて、必要ない場所の照明は消し、
部屋全体を明るくしないように心がけてみるだけで、
子どもの脳の発達は随分促進されるはず。
知っていれば済む話です。
子どもの脳の成長のためにも、
お部屋の照明、見直してみませんか?
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
睡眠の悩みは尽きないですが、
日常のちょっとした工夫が突破口になることがあります。
この本では、誰でも今日から簡単にできる
科学的な睡眠の作り方を詳しくご説明しています。
毎日の生活の充実に、
ぜひご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
11:08
│Comments(0)
2013年04月08日
朝じっくり夕方サクサクで仕事効率アップ!
頭の回転が速い人にはあこがれます。
パパっと切り替えて仕事をこなす様子は、
見ているだけで気持ちが良いですね。
近づきたい。
そこで、まずは自分の足元から見ていきましょう。
人をうらやむより、まず自分の資源をフル活用してみます。
頭の回転にも生体リズムがあります。
私たちにもともと備わったリズムに、
普段行っている仕事をマッチさせればよいわけです。
もとは1980年代に行われた古い実験ですが、
ある作業を行い、その正確さと達成度の1日の移り変わりを
見たという実験結果から、ヒトの作業にも
リズムがあることが明らかにされてきています。
この実験の結果から。
より正確性を求められる慎重な作業は
起床してから4時間までの間がピークで、
夜に向かって段々低下します。
反対にスピードが要求される作業は
午前から徐々に高まり夕方がピークです。
別の知見より、
起床から4時間以内は脳波活動が活発であり、
夕方は心臓と肺の効率が最高になるという事実があります。
ということは、やはりヒトの作業にもリズムがあると
考えてよさそうですね。
朝はバタバタして片付けからはじめたり、
メールの整理などに時間をとられてしまいがち。
また夕方は、その日の返答待ちの案件や
翌日の作戦を練るためにじーっと考えたりしがちです。
このリズムでは、朝はカラダに、夕方は脳に負担が
かかってしまうので、疲労しやすく、
仕事の効率は悪くなってしまいます。
できる部分から、
いつもの仕事のパターンを少しだけ変えてみませんか?
「朝はじっくり夕方は手早く」を意識して
仕事の配分をすれば効率アップ!です。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
生体リズムを活かすためにもっとも効果があり、
もっとも簡単に使える現象が睡眠です。
おかげさまで、12刷、
4万部を突破いたしいました。
毎日をより充実させたいすべての方々に。
ぜひ、お役立てください。
パパっと切り替えて仕事をこなす様子は、
見ているだけで気持ちが良いですね。
近づきたい。
そこで、まずは自分の足元から見ていきましょう。
人をうらやむより、まず自分の資源をフル活用してみます。
頭の回転にも生体リズムがあります。
私たちにもともと備わったリズムに、
普段行っている仕事をマッチさせればよいわけです。
もとは1980年代に行われた古い実験ですが、
ある作業を行い、その正確さと達成度の1日の移り変わりを
見たという実験結果から、ヒトの作業にも
リズムがあることが明らかにされてきています。
この実験の結果から。
より正確性を求められる慎重な作業は
起床してから4時間までの間がピークで、
夜に向かって段々低下します。
反対にスピードが要求される作業は
午前から徐々に高まり夕方がピークです。
別の知見より、
起床から4時間以内は脳波活動が活発であり、
夕方は心臓と肺の効率が最高になるという事実があります。
ということは、やはりヒトの作業にもリズムがあると
考えてよさそうですね。
朝はバタバタして片付けからはじめたり、
メールの整理などに時間をとられてしまいがち。
また夕方は、その日の返答待ちの案件や
翌日の作戦を練るためにじーっと考えたりしがちです。
このリズムでは、朝はカラダに、夕方は脳に負担が
かかってしまうので、疲労しやすく、
仕事の効率は悪くなってしまいます。
できる部分から、
いつもの仕事のパターンを少しだけ変えてみませんか?
「朝はじっくり夕方は手早く」を意識して
仕事の配分をすれば効率アップ!です。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
生体リズムを活かすためにもっとも効果があり、
もっとも簡単に使える現象が睡眠です。
おかげさまで、12刷、
4万部を突破いたしいました。
毎日をより充実させたいすべての方々に。
ぜひ、お役立てください。
Posted by ActiveSleep at
08:43
│Comments(0)
2013年04月04日
成長ホルモンは空腹にならないと出ない
お腹が空いたーというときは、
自然に気分が上向きになるもの。
普段から間食が多いと、空腹がよく分からなくなって、
お腹がすくとイライラするサイクルに
なってしまいます。
空腹時に分泌が増える
グレリンというホルモンがあります。
このグレリンはとても多彩な作用があります。
その作用の1つが、
成長ホルモン分泌刺激作用です。
成長ホルモンは、
美容として注目されるように、
蛋白質、炭水化物、脂肪の代謝作用が
あります。
機能異常で増えすぎると、抗インシュリン作用があり
糖尿病誘発作用を促すこともあります。
ホルモンは全てバランスで成り立っているので、
全てによい作用というわけには
いかないのは当然ですね。
空腹になるとグレリンが増えて、
成長ホルモンが増える。
健康な体を保つには、とても大切なサイクルです。
ところが、
私たちが空腹を感じるには、
それを邪魔する強敵がいます。
それは90分ごとに訪れる
口さびしいという感覚です。
時計遺伝子の働きによって、
90分ごとに、のどが渇いたり
口さびしくなったりします。
ここで間食をしてしまうと、
本来の空腹は、わからなくなってしまいます。
お腹が空いているのかどうか
よく分からないという事態には、
みなさん遭遇したことがあると思います。
空腹感、大切にしたいものです。
この空腹感を回復させるために、
食べ放題を使う治療方法もあるほどです。
お腹がすいたら好きなだけ食べて、
その後から絶食する。
昼だから夜だからと、いつもの時間に食べることを
せずに、おなかがすいたら食べるという
感覚を取り戻すという方法です。
随分荒っぽいやり方ですが、
普段の生活でも意図的に絶食時間をつくることは
できます。
次の空腹がくるまで食べない。
こうして本当の空腹感を取り戻すことが、
現代の飽食生活とうまく付き合う
ポイントですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
おかげさまで、重版を重ね、
11版になりました。
忙しい毎日でも、
脳と体の仕組みが分かれば充実できます。
睡眠は食事、運動の効果を本物にする
最高のツールです。
ぜひ、ご活用ください。
自然に気分が上向きになるもの。
普段から間食が多いと、空腹がよく分からなくなって、
お腹がすくとイライラするサイクルに
なってしまいます。
空腹時に分泌が増える
グレリンというホルモンがあります。
このグレリンはとても多彩な作用があります。
その作用の1つが、
成長ホルモン分泌刺激作用です。
成長ホルモンは、
美容として注目されるように、
蛋白質、炭水化物、脂肪の代謝作用が
あります。
機能異常で増えすぎると、抗インシュリン作用があり
糖尿病誘発作用を促すこともあります。
ホルモンは全てバランスで成り立っているので、
全てによい作用というわけには
いかないのは当然ですね。
空腹になるとグレリンが増えて、
成長ホルモンが増える。
健康な体を保つには、とても大切なサイクルです。
ところが、
私たちが空腹を感じるには、
それを邪魔する強敵がいます。
それは90分ごとに訪れる
口さびしいという感覚です。
時計遺伝子の働きによって、
90分ごとに、のどが渇いたり
口さびしくなったりします。
ここで間食をしてしまうと、
本来の空腹は、わからなくなってしまいます。
お腹が空いているのかどうか
よく分からないという事態には、
みなさん遭遇したことがあると思います。
空腹感、大切にしたいものです。
この空腹感を回復させるために、
食べ放題を使う治療方法もあるほどです。
お腹がすいたら好きなだけ食べて、
その後から絶食する。
昼だから夜だからと、いつもの時間に食べることを
せずに、おなかがすいたら食べるという
感覚を取り戻すという方法です。
随分荒っぽいやり方ですが、
普段の生活でも意図的に絶食時間をつくることは
できます。
次の空腹がくるまで食べない。
こうして本当の空腹感を取り戻すことが、
現代の飽食生活とうまく付き合う
ポイントですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
おかげさまで、重版を重ね、
11版になりました。
忙しい毎日でも、
脳と体の仕組みが分かれば充実できます。
睡眠は食事、運動の効果を本物にする
最高のツールです。
ぜひ、ご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
08:41
│Comments(0)
2013年04月03日
自分らしさは一緒にいる人につくられる
人間関係って不思議ですね。
几帳面な人と大雑把な人が一緒に暮らすと
段々性格が入れ替わってきます。
大雑把な人がココアを入れるときに、
スプーンで測っちゃったりして。
几帳面な人は袋から直接入れちゃったりして。
脳の中では
ミラーニューロンと呼ばれる神経レベルで
この作用が生まれています。
ミラーニューロンの作用は、
「見た」ときに脳内で「手を動かす」ことをします。
例えば、
マグカップを見ます。
すると、脳内では、マグカップの取ってを
持つときの手の形をつくり手を伸ばしてマグカップを持つ。
もちろん脳内の話なので、実際には
手はまだ動いていません。
この機能によって、
マグカップをとろうとすると、
取る前から手はマグカップの取っ手に適した形に
なっています。
これで私たちはスムーズに動作できるわけです。
この「見る」ことで「手を動かす」機能によって、
一緒にいる人のしぐさ、しゃべり方、思考が
うつります。
憧れの人のそばにいると自分が高まるとか、
バカはうつるとか、そんな話をよく聞きますが、
実際にそう。
私たちは自分らしさを探し求めますが、
自分らしさは、かなり一緒にいる人によって
つくられています。
今、隣にはどんな人がいますか?
自分をつくるのを相手であれば、
相手も自分によってつくられています。
色んな習慣をもった人たちと過ごすことは、
自分の脳内のパターンが増えるということ。
年齢を重ねていくと、
自分とは違う習慣をもった人と過ごすのは
億劫になりますが、自分を変えたいなと思ったときは、
普段行かないような場所に身を置いてみては
どうでしょう。
脳が勝手に新しい動作のパターンを
つくっていきます。
自分を変える。
すごくテンションが高く、大変なことのようですが、
脳の仕組みに従ってみると、
案外、ちょっとしたことで変化は起こるものですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
眠り方ほど、
その人の習慣が顕著に出る場面はありません。
みなさん、様々な自分なりの習慣や儀式をもっています。
自分の習慣を無理に変える必要はありません。
脳には普遍的な事実がありますので、
それを知ったうえで、今の自分の生活にうまく
活かしていきましょう。
几帳面な人と大雑把な人が一緒に暮らすと
段々性格が入れ替わってきます。
大雑把な人がココアを入れるときに、
スプーンで測っちゃったりして。
几帳面な人は袋から直接入れちゃったりして。
脳の中では
ミラーニューロンと呼ばれる神経レベルで
この作用が生まれています。
ミラーニューロンの作用は、
「見た」ときに脳内で「手を動かす」ことをします。
例えば、
マグカップを見ます。
すると、脳内では、マグカップの取ってを
持つときの手の形をつくり手を伸ばしてマグカップを持つ。
もちろん脳内の話なので、実際には
手はまだ動いていません。
この機能によって、
マグカップをとろうとすると、
取る前から手はマグカップの取っ手に適した形に
なっています。
これで私たちはスムーズに動作できるわけです。
この「見る」ことで「手を動かす」機能によって、
一緒にいる人のしぐさ、しゃべり方、思考が
うつります。
憧れの人のそばにいると自分が高まるとか、
バカはうつるとか、そんな話をよく聞きますが、
実際にそう。
私たちは自分らしさを探し求めますが、
自分らしさは、かなり一緒にいる人によって
つくられています。
今、隣にはどんな人がいますか?
自分をつくるのを相手であれば、
相手も自分によってつくられています。
色んな習慣をもった人たちと過ごすことは、
自分の脳内のパターンが増えるということ。
年齢を重ねていくと、
自分とは違う習慣をもった人と過ごすのは
億劫になりますが、自分を変えたいなと思ったときは、
普段行かないような場所に身を置いてみては
どうでしょう。
脳が勝手に新しい動作のパターンを
つくっていきます。
自分を変える。
すごくテンションが高く、大変なことのようですが、
脳の仕組みに従ってみると、
案外、ちょっとしたことで変化は起こるものですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
眠り方ほど、
その人の習慣が顕著に出る場面はありません。
みなさん、様々な自分なりの習慣や儀式をもっています。
自分の習慣を無理に変える必要はありません。
脳には普遍的な事実がありますので、
それを知ったうえで、今の自分の生活にうまく
活かしていきましょう。
Posted by ActiveSleep at
08:20
│Comments(0)



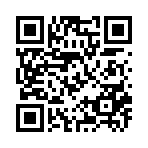

 Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved
