2013年08月29日
つくり笑いは脳にとっても不自然な運動
おはようございます。
楽しくて笑うときとつくり笑いの違いは?
つくり笑いをしていると、
片方の口角だけが上がったり、目が笑っていないなど
ひきつった顔になってしまいます。
前者は、
前頭基底ループが活発になっています。
ここは、補足運動野、被殻といった自動化された運動を
出力する部位。
自然に顔が動いてしまうということです。
一方、後者は、
一次運動野が活発になります。
ここは、新しい運動を意図的に出力する部位。
つまりあえて脳が筋肉に命令して顔を動かしています。
どおりでひきつるわけです。
この一次運動野を使ったつくり笑いをしていると、
顔の筋肉の運動が自動化されていかずに
骨と筋肉のポジションに無理が生じて、
その結果、ほうれい線が深くなるとも言われています。
楽しくて笑う、ということは、
脳にとってはごく自然な運動出力だということですね。
さて、
無理に楽しもうとしても、
笑えないこともあります。
笑いをとろうとしてすべったときの、
会場のシーンという空気は独特なものがありますよね。
ギャグがすべったときは
聞いている人の脳では、
腹内側前頭眼窩野の活動が著しく低下します。
この部位は、楽しくて笑うことに深く関係しているだけでなく、
私たちが何かをしたいと自発的な動機をもつ部位でもあります。
自分から動こうという部位が低下するので、
まさにシーンとしています。
楽しい笑いは、
歩くことや食べることなどの
自動化された運動と同じレベルです。
ごく自然に毎日の生活の中で
楽しく笑いたいものですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
毎日行っている睡眠。
これもただ眠らずに仕組みを知ることで、
俄然楽しい活動になります。
こちらの本では、
睡眠の仕組みを詳しくご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひお役立てください。
Posted by ActiveSleep at
08:40
│Comments(0)
2013年08月28日
能力が高いほどプレッシャーでミスをする!?
おはようございます。
無知で無鉄砲なときほど
いい結果を出すことがあります。
知識と経験が身につくほど
強いプレッシャーを感じてミスをすることがあるのは
なぜでしょう。
知力が高いほどプレッシャーで
ミスが多いという研究があります。
頭の中で記憶しながら同時進行で作業する
ワーキングメモリー。
この機能が高いと
マルチタスクでも作業は正確です。
ところが能力が高いと
それを使いたがる反応が起こる。
プレッシャー下でも
適当に手を抜いて作業を進めずに、
むしろ持っている能力を存分に発揮しようと
することでミスをする。
あまりに狙い過ぎると
何事もうまくいかないというのは、
脳内で高い能力を動員しすぎた結果という
ことでしょうか。
この反応は一息つくと低下するとのこと。
難しい課題を次々こなしているときは、
どんどんエスカレートしていく感じがあります。
課題をやっつけると「次はどいつだ!」みたいな
気分になって、自分の持てる能力を
思い知らせたく(誰にだ?)なること、
ありませんか?
この反応に慣れていると、
プレッシャーがかかっているときに
「やってやろう!」とし過ぎて、
良い結果が出ない。
知力が必要なときほど
一旦その課題から離れてみることが
良い結果を生むコツなのかもしれませんね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
自分の能力はフル活用したいですが、
どうやら使い方があるようですね。
こちらの本では、
忙しい生活でも押さえるポイントだけ押さえて
後は自由。という調整で睡眠の質を高める方法を
ご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
08:54
│Comments(0)
2013年08月27日
なぜ子供に口うるさく言ってしまうのか
おはようございます。
何らかの作業をしているときは
無意識でも脳内で段取りを立てています。
過去の記憶から
行動予定を立てる内側ネットワークの働き。
しかし、
このタイミングで「○○やったの?」と声をかけられると
段取りが狂いイラッと。
「今やるとこ!(怒)」
どんなに良い方法であっても、
脳内の段取りが狂わされるのは負担がかかります。
行動予定を修正するには、
今までの行動を抑制しながら、
新しく言われたことから行動を組み立てなければ
ならないです。
一方、声をかけている側は、というと、
声かけをすればするほど
どんどんエスカレートしていきます。
自分のことをしながら周囲を見渡し、
相手の行動で、自分のイメージと違うものを見つけたら
声をかける。
こうしていると、
本人は実に充実感を得ます。
自分の行動と周囲の監視、声かけによる介入という
マルチタスクによって脳が過剰に興奮し、
新たな間違いを発見するのを期待してしまうのです。
これはドーパミンの作用。
ドーパミンは、分泌された前の行動を強化します。
つまり、声かけをし続ける。
相手の間違いを待ち続ける。
これって、
子育てにはよく見られる場面です。
自分に置き換えてみると、
実に口うるさく子供が行動する前に
口を出してしまう。
口を出す目的は、子供に成長してほしいから。
でも、本当に成長するには、
脳内で組んだ予定通りに行動を完結させて
上げることのはず。
そこで、
完成のイメージだけを伝えて、
手順は任せてみてはいかがでしょう。
自分は、不得意だから
うまいこと人に手伝ってもらいたいな
という場面だと置き換えてみるといいかもしれません。
(本当は得意だけど)
こんな風にやってくれないかなー。
くらいのテンションで子供に伝えれば、
子供は一生懸命自分なりの段取りで行動してくれます。
お互いに成長できるコミュニケーションを
とっていきたいですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
脳の仕組みが分かると
毎日のちょっとした行動にも
チャンスがあります。
こちらの本では、
脳を活かすツールとして
睡眠を活用する方法を
詳しくご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひお役立てください。
Posted by ActiveSleep at
10:35
│Comments(0)
2013年08月26日
いつも眠いロングスリーパーの勘違い!?
おはようございます。
すぐに眠れて、
いつも眠い、
休日はいくらでも眠れる。
そんな自分は
ロングスリーパーだと思っていらっしゃる方が
多いです。
・ベッドに入ってから5分以内に眠れる
・起床から4時間後に眠気がある
・休日は平日より長く眠る
実は、これらは慢性的な睡眠不足の兆候です。
時間数は眠っているのですが、
深い睡眠をつくれていない。
最初の3時間に深い睡眠がつくれないと
後どれだけ睡眠時間を伸ばしても
体は回復しません。
深い睡眠が出現するのは、
90分サイクルの最初に2回のみ。
そして、
身体を回復させる成長ホルモンは、
睡眠の深さに依存します。
深くなれば成長ホルモンが出る。
逆に、最初の深さをつくれなければ、
どれだけ伸ばしても体がだるくなるばかりで、
結果的に、いつもぐっすり眠ってもいないし、
しゃっきり起きてもいない、
睡眠と覚醒のはざまのような状態になってしまいます。
「私はロングスリーパーだから」
と決めつけてしまうと、この悪循環から
抜け出せません。
そこで、
最初の90分にしっかりと
深い睡眠をつくってみましょう。
やり方は簡単です。
就寝1時間前に何らかの体操をしましょう。
内臓の温度である深部体温を上げるには、
熱産生器官である筋肉を使うのが効果的。
そこで、
今まで実施したことがある体操なら
何でもよいので、就寝1時間前、
できれば入浴前に1分でも実施してみましょう。
体操→入浴→1時間後に就寝
このサイクルで、
最初の深い睡眠をつくることができれば、
身体は回復し、それほど長く眠れなくなっていきます。
生体リズムをしっかり助けて、
身体の機能をフル活用しましょう。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
こちらでは、
生体リズムを活用した
睡眠の作り方を詳しくご紹介しています。
忙しい毎日でも
誰でも簡単にできる方法です。
毎日の充実に
ぜひご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
09:02
│Comments(0)
2013年08月23日
脳科学という言葉で信頼性が上がってしまう!?
おはようございます。
脳科学的な表現が文章に入ると
情報の質を適正に判断できなくなると。
これは「ジンクピリチオン効果」と命名されています。
言葉の音感と新規性に信頼度が増す。
意味が不明瞭な用語がつくと、
それを聞いた一般の人は信頼度が上がり、
逆にそれを聞いた専門家の信頼度は下がるとのこと。
「ジンクピリチオン配合!」みたいな
フレーズがつくと「おお!なんかすごそう!」という
反応が起こるというものです。
これは
脳科学という用語においても同じような作用がある。
例えば、
「テレビを見ると数学が得意になる。
なぜならテレビを見ているときには
数学と同じ場所の脳の部位が活性化するからだ」
そして脳画像やグラフが並ぶと
「なるほどー」と。
イヤイヤないない(笑)
脳科学という言葉には中身の説明なしに
信頼度を高める作用がある。
このことを知った上で、
情報とうまく付き合っていきたいですね。
脳が画像化されて、2000年以降に
精神疾患は心が弱い人がなるのではなく、
脳の疾患なのだという認識が広まったということは、
とても画期的なことでした。
見えなかったものが見えるようになる。
しかし、見えたことによって、
見えなかったときのような詳細な考察が省かれてしまうのは、
上記のような弊害を生み出す可能性があります。
脳、というと特別な存在な気がしますが、
脳も単なる内臓です。
脳画像を胃カメラの画像と同じような目線で
見ていただくと、
脳が活性化という言葉だけで「なるほど!」とは
思わないと思います。
情報は自分を前進させるためのもので
あってほしいですよね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
この本は、
脳の働きを高めるために睡眠を活用するという
視点から、脳と睡眠の仕組みを詳しくご紹介しています。
これも脳の情報です。
ただ鵜呑みにするのではなく、
ご自分の生活を前進させることができる情報なのかを
しっかりと吟味して読んでいただけたらうれしいです。
Posted by ActiveSleep at
09:24
│Comments(0)
2013年08月21日
ストレスは脳内で再固定中にすり替えを
おはようございます。
作業療法士の菅原洋平(すがわらようへい)です。
皆さんは、嫌なことがあったらどうしますか?
嫌な記憶を消したい。そんなときもありますよね。
記憶は、一旦脳に固定されて、
再検索されたときに再固定されます。
この再検索のカギになるのが
「場所」です。
この場所がリマインダーとして、
記憶を呼び出し、脳内に再固定します。
これがストレス再燃、
つまり、「あーいやなこと思い出しちゃったー」
という状態です。
嫌なことから切り替えたいときは、
この脳内で再固定されるときに消去をする。
記憶の消去とは、
消すことではなく、書き換えることです。
ラットの研究では、
ストレスを受けてその場に数日居続けた場合、
ストレスを受けた直後ではなく、
数日後に恐怖反応が増強することが
明らかになっています。
再固定されたときにストレスが再燃する。
そこで、
「いやだな」とストレスを感じたら、
次にその場所で、
わざと好きなことをしたり、好きな人と話したり
してみては。
日常のちょっとした記憶の書き換えで、
脳内が前向きに書き換えられる反応が
つくれるかもしれませんね。
ところで、
この脳が場所で記憶を固定する性質が、
睡眠に大きく関係しています。
ベッドでスマホ、PC、ゲーム、小説などなど、
眠りに無関係なことをしていますと、
次にベッドにいったときに、
この場所は活動する場所だという記憶が再固定されて、
なかなか睡眠に入りにくい脳の構造が
出来上がってしまいます。
寝つきが悪い、眠った気がしないという方は、
ベッドの上で眠る以外のことをしない、
ということを心掛けてみてはいかがでしょうか。
眠る前にメールを出さなければならないときは、
ベッドの横に椅子を置き、
その椅子でメールを書いたら、
椅子にスマホを置いてベッドに入る。
こうするだけで、
ベッド=眠りという反応を
脳内につくっていくことができます。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
睡眠は、脳の活動を活発にするために
使える手軽なツールです。
こちらの本では、
「起床から4時間以内に光を見て、
6時間後に目を閉じ、
11時間後に姿勢を良くする」というちょっとした工夫で、
生体リズムを整え、睡眠を促進させる方法を
ご紹介しています。
仕組みが分かれば、
毎日の生活はもっと充実しますね。
Posted by ActiveSleep at
06:54
│Comments(0)
2013年08月20日
知らないふりは知ったかぶりより後ろめたい!?
おはようございます。
会話中にときどきみられるのが、
知ったかぶりや知らないふりをすること。
知ったかぶり、知らないふり。
そのどちらをしているときも前頭前野の各部位が働きます。
左背外側前頭前野、右腹外側前頭前野、右背内側前頭前野。
主に抑制を司るこれらの部位は、
事実をぐっと抑制して違うことを言うという
脳の活動を表していると考えられます。
落語「千早ふる」のように
知ったかぶりは見ていて笑えます。
本人もどうしよう・・・と引っ込みがつかない感じで
ほほえましいこともありますし、
それは話を盛り過ぎ!と聞いている方も
分かりやすいこともあります。
一方で、知らないふりは
陰湿さや悪意を感じることもあります。
知らないふりは、上記の脳部位に加えて
右前部帯状回の活動も活発になっています。
これは、過去の記憶に対する葛藤が含まれる表れ。
知らんぷりの方が後ろめたさがあるという
ことかもしれませんね。
それにしても神経活動をみると、
どちらも随分エネルギー使っています。
このエネルギーの使い道、
間違えたくないですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
脳の仕組みが分かると、
毎日の些細な場面が違って見えてきます。
こちらの本では、
睡眠を脳を活用するツールとして
とらえてご紹介しています。
毎日の生活の充実に、
ぜひご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
08:52
│Comments(0)
2013年08月19日
現金報酬より仮眠の方が脳力アップ!?
おはようございます。
注意力の研究では
人の注意力は午前がピークで
どんどん低下していくことが知られています。
脳波活動が最もピークなのは、
起床4時間後。6時おきの人は10時です。
そんな午前中から午後にかけて下がる
注意力を保ち続けるにはどうすればよいのでしょう?
皆さんは
社員の人にきっちり働いてもらいたかったら、
どうしますか?
この仕事を終えたら特別ボーナス!
みたいな現金報酬を考えるのが一般的だと思います。
この研究では、
1日に4回注意力テストが行われました。
午前が一番注意力が高く、
午後にかけて低下していく。
そこで、現金報酬を与える条件にしましたが、
注意力は改善しませんでした。
ところが、
2回目のテストと3回目のテストの間、
昼の時間帯に30分の仮眠をとる条件にすると、
注意力は低下せず、むしろ向上することも
みられたということです。
つまり、
社員にきっちり働いてもらうには、
現金報酬より仮眠が有効と。
これは
価値観を覆されるような結果ですね。
社員の立場では
報酬をもらうと気分は盛り上がりますが、
それで作業がはかどるわけではない。
というのはなんとなくわかる気がします。
それとこれとは別。みたいな。
ところが
人をやる気にさせなければならない場面では、
報酬を与えるという選択をする方が
ほとんどだと思います。
その場限りのやる気より
客観的な能力アップができる方法を
選びたいですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
睡眠を科学的にとらえると、
私たちの仕事を向上させるヒントが
見えてきます。
こちらの本では、
生体リズムを活用した
誰でもできるやる気が出る方法を
詳しくご紹介しています。
毎日の充実に
ぜひ、お役立てください。
Posted by ActiveSleep at
07:13
│Comments(0)
2013年08月08日
散歩中にひらめく脳の仕組み
おはようございます。
単純作業中にひらめくことがあります。
デキる人は、意図的に集中した後、
単純作業を割り当てていたりもします。
脳には注意資源配分があります。
たとえば、
右視野に注意を向けると左半球が高まり
そのとき同時に右半球の活動低下します。
ある部位に資源を
動員するために他の部位からかき集めるような仕組みです。
複雑なことを学んでいたり、
難しい課題中は、
脳内の資源を総動員しています。
とても他の部位を使っている暇などない。
一方で、
単純作業中は、脳内の資源が余っているので、
脳内の思考(内的思考)に当てられます。
ここで、
マインドワンダリング
(とりとめないことがふと浮かぶ)が起こる。
これがひらめきになることが。
ギュッと集中後に
散歩、皿洗い、掃除など、
日常の中でやり慣れた単純作業をすれば
いいアイデアひらめく!
脳の働きをうまく活用して、
しびれるアイデアを提案しちゃいましょう!
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
仕組みが分かれば、
今の自分を向上させる方法が見えてきます。
この本では、
毎日のちょっとした工夫で
睡眠を活用してやる気が湧き出る方法を
詳しくご紹介しています。
毎日の充実にぜひ、お役立てください。
Posted by ActiveSleep at
07:18
│Comments(0)
2013年08月05日
夜過ごすリビングでメラトニンが減ってしまう!?
おはようございます。
睡眠の質を上げるには
夜暗くすることが大切です。
暗くなると分泌される
メラトニンをしっかり増やして、
眠気を促し、睡眠中の抗酸化作用で
活性酸素を除去してもらうためです。
私たちは、夜暗くする、と聞くと
寝室の照明ばかり気にしがちですが、
実は、リビングが大切。
夜過ごすリビングが
蛍光灯シーリングライトだと大体室内は
500ルクスの明るさです。
500ルクスの明るさの部屋で、
3時間過ごすと、
出るはずのメラトニンは50%まで
減少してしまいます。
19時以降過ごす部屋は
電球色か間接照明にすることが
メラトニンを増やして、睡眠の質を上げるコツです。
このメラトニンが減ってしまう率は、
大人より子どもの方が高いです。
一緒の部屋で過ごしている
母と子のメラトニン量を調べた研究では、
子どもの方がメラトニンが減ってしまっていました。
子どもは、
光に対する感受性が強いので、
しっかり眠れる環境は、
大人が作ってあげたいですね。
この本では、
睡眠の仕組みを知り、
忙しく、不規則な生活でも
質を高めて、昼間のパフォーマンスを上げる
方法を詳しくご紹介しています。
毎日の充実に、
ぜひ、ご活用ください。
睡眠の質を上げるには
夜暗くすることが大切です。
暗くなると分泌される
メラトニンをしっかり増やして、
眠気を促し、睡眠中の抗酸化作用で
活性酸素を除去してもらうためです。
私たちは、夜暗くする、と聞くと
寝室の照明ばかり気にしがちですが、
実は、リビングが大切。
夜過ごすリビングが
蛍光灯シーリングライトだと大体室内は
500ルクスの明るさです。
500ルクスの明るさの部屋で、
3時間過ごすと、
出るはずのメラトニンは50%まで
減少してしまいます。
19時以降過ごす部屋は
電球色か間接照明にすることが
メラトニンを増やして、睡眠の質を上げるコツです。
このメラトニンが減ってしまう率は、
大人より子どもの方が高いです。
一緒の部屋で過ごしている
母と子のメラトニン量を調べた研究では、
子どもの方がメラトニンが減ってしまっていました。
子どもは、
光に対する感受性が強いので、
しっかり眠れる環境は、
大人が作ってあげたいですね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
この本では、
睡眠の仕組みを知り、
忙しく、不規則な生活でも
質を高めて、昼間のパフォーマンスを上げる
方法を詳しくご紹介しています。
毎日の充実に、
ぜひ、ご活用ください。
Posted by ActiveSleep at
07:26
│Comments(0)



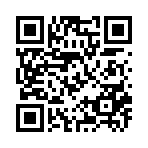

 Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved