2012年03月30日
働く女性は昼間眠い!
勤労者の睡眠調査では、
日中に過度の眠気を自覚する女性は13.3%。
男性の7.2%に比べて約2倍です。
関連する因子として、
6時間未満の睡眠時間であること
起床時間が不安定であること
抑うつ傾向であること
が挙がっています。
女性の月経周期にともなう24時間の眠気を
脳波で調べたところ、
月経前の黄体期では、日中に徐波睡眠の
出現回数が増加していることがわかりました。
女性が自覚する眠気は、
科学的にも裏付けられています。
仕事上は、
うっかりミスや物忘れが増えるというリスクが
高まります。
女性の眠気の変化に合わせて、
仕事のスケジュールが組まれれば、
日本のうつ病問題は
かなり解決しそうですよね。
この女性型社会というべきか、
女性の生理現象に合わせた
社会のリズムが望ましいということは、
かなり以前から学会などで報告されています。
実は、このリズム、
男性にも利点が多いのです。
あまり知られない、
男性の更年期障害や
うつ病などには、
生体のリズムのずれと
社会のリズムのずれが
関係していると考えられています。
男性は自覚できにくいので、
科学的な証明が進んでくれば、
生理的なリズムを尊重した
ヒトの能力がもっとも発揮される
労働スケジュールが実現できるかも
しれません。
そんな社会を目指したいですね。
日中に過度の眠気を自覚する女性は13.3%。
男性の7.2%に比べて約2倍です。
関連する因子として、
6時間未満の睡眠時間であること
起床時間が不安定であること
抑うつ傾向であること
が挙がっています。
女性の月経周期にともなう24時間の眠気を
脳波で調べたところ、
月経前の黄体期では、日中に徐波睡眠の
出現回数が増加していることがわかりました。
女性が自覚する眠気は、
科学的にも裏付けられています。
仕事上は、
うっかりミスや物忘れが増えるというリスクが
高まります。
女性の眠気の変化に合わせて、
仕事のスケジュールが組まれれば、
日本のうつ病問題は
かなり解決しそうですよね。
この女性型社会というべきか、
女性の生理現象に合わせた
社会のリズムが望ましいということは、
かなり以前から学会などで報告されています。
実は、このリズム、
男性にも利点が多いのです。
あまり知られない、
男性の更年期障害や
うつ病などには、
生体のリズムのずれと
社会のリズムのずれが
関係していると考えられています。
男性は自覚できにくいので、
科学的な証明が進んでくれば、
生理的なリズムを尊重した
ヒトの能力がもっとも発揮される
労働スケジュールが実現できるかも
しれません。
そんな社会を目指したいですね。
Posted by ActiveSleep at
06:52
│Comments(1)
2012年03月29日
ヒトの行動は90分単位?!
睡眠は90分周期になっていると
いう話を聞いたことがあると思います。
実は、睡眠だけではなく、
昼間の活動も約90分の周期があります。
胃の蠕動運動も約90分ごとです。
食べ物(ちょっとしたものをつまみたくなる)も
飲み物(ちょっとのどが渇いた感じがする)も
90分ごとに欲するリズムがあります。
排尿も90分ごと。
忙しくてトイレにいけないでいると、
夜間にその分を補うシステムが働くので、
90分ごとに目覚めてしまいます。
喫煙など口唇性行動も。
講義の休憩のたびに煙草を吸いに行く学生は
分かりやすい行動ですね。
考えが浮かぶ空想(新しいことが思い浮かぶ)する
のも90分ごと。
人の話を聞いていたつもりなのに、
頭の中では違うことを考えてしまうのも
90分ごとです。
作業時の脳波の振幅も。などなど。
とにかく、ありとあらゆる生理現象が、
約90分のリズムをもっていることが
分かってきています。
なぜこのようなリズムが?
これには、太陽から出される
見えない光線(宇宙線)が関与している
という考えがあります。
壮大な話です。
さておき、
私たち庶民は、
90分ごとに軽く休憩をとって、
自分の頭の働きを高めていきましょう。
いう話を聞いたことがあると思います。
実は、睡眠だけではなく、
昼間の活動も約90分の周期があります。
胃の蠕動運動も約90分ごとです。
食べ物(ちょっとしたものをつまみたくなる)も
飲み物(ちょっとのどが渇いた感じがする)も
90分ごとに欲するリズムがあります。
排尿も90分ごと。
忙しくてトイレにいけないでいると、
夜間にその分を補うシステムが働くので、
90分ごとに目覚めてしまいます。
喫煙など口唇性行動も。
講義の休憩のたびに煙草を吸いに行く学生は
分かりやすい行動ですね。
考えが浮かぶ空想(新しいことが思い浮かぶ)する
のも90分ごと。
人の話を聞いていたつもりなのに、
頭の中では違うことを考えてしまうのも
90分ごとです。
作業時の脳波の振幅も。などなど。
とにかく、ありとあらゆる生理現象が、
約90分のリズムをもっていることが
分かってきています。
なぜこのようなリズムが?
これには、太陽から出される
見えない光線(宇宙線)が関与している
という考えがあります。
壮大な話です。
さておき、
私たち庶民は、
90分ごとに軽く休憩をとって、
自分の頭の働きを高めていきましょう。
Posted by ActiveSleep at
08:34
│Comments(0)
2012年03月28日
眠ってヤセる!
寝ないとお化けが出るよ!
と子どもに言いますが、
本当に出るのは成長ホルモンです。
成長ホルモンというと、
思春期の成長期を思い浮かべますが、
大人になっても成人になっても分泌されます。
成長ホルモンには、
あまり知られていない働きがあります。
①糖分と脂肪分を燃焼させる
②ストレスで傷ついた神経を修復する
①眠るには体力が必要です。
それだけ代謝がされるのです。
年齢を重ねていくと、
必要な睡眠時間が短くなって
いくのは、体力が低下していくからです。
代謝では、
糖分と脂肪分を燃焼させています。
ダイエットでは、
燃焼させることに一生懸命。
飲料や食べ物でも
燃焼させる商品を買っている。
でも、眠っている間の
脂肪燃焼を無駄にしてしまうのは、
ちぐはぐなダイエットになってしまいます。
②は、ストレス。
ストレスというと、
研修などでは風船を例に出されると思います。
風船をギュッと上から押し付けた
状態がストレス。などという説明です。
医学的には、ストレスとは
神経の損傷です。
けがをしたわけではないのに、
神経が損傷するのか?と
思われるかもしれませんが、
神経はいつも損傷したり、
死滅しています。
プレッシャーがかかると
神経の損傷が、
神経の再生より上回り、
その状態が慢性化するので
ストレスによって身体に
不調が現れます。
成長ホルモンは、
そんな神経を修復する働きを
しています。
うまくいかないことがあったら、
寝てしまおう!と対処されている人が
いらっしゃると思いますが、
すごく良い対処です。
成長ホルモンが分泌されるのは、
眠ってから3時間が最大。
体温が下がれば下がるほど、
分泌は増えます。
そこで、
眠る1時間前に、
汗ばむ程度のエクササイズを5分ほど。
ストレッチや簡単な筋トレでも結構です。
翌朝の熟眠感が変わってきます。
と子どもに言いますが、
本当に出るのは成長ホルモンです。
成長ホルモンというと、
思春期の成長期を思い浮かべますが、
大人になっても成人になっても分泌されます。
成長ホルモンには、
あまり知られていない働きがあります。
①糖分と脂肪分を燃焼させる
②ストレスで傷ついた神経を修復する
①眠るには体力が必要です。
それだけ代謝がされるのです。
年齢を重ねていくと、
必要な睡眠時間が短くなって
いくのは、体力が低下していくからです。
代謝では、
糖分と脂肪分を燃焼させています。
ダイエットでは、
燃焼させることに一生懸命。
飲料や食べ物でも
燃焼させる商品を買っている。
でも、眠っている間の
脂肪燃焼を無駄にしてしまうのは、
ちぐはぐなダイエットになってしまいます。
②は、ストレス。
ストレスというと、
研修などでは風船を例に出されると思います。
風船をギュッと上から押し付けた
状態がストレス。などという説明です。
医学的には、ストレスとは
神経の損傷です。
けがをしたわけではないのに、
神経が損傷するのか?と
思われるかもしれませんが、
神経はいつも損傷したり、
死滅しています。
プレッシャーがかかると
神経の損傷が、
神経の再生より上回り、
その状態が慢性化するので
ストレスによって身体に
不調が現れます。
成長ホルモンは、
そんな神経を修復する働きを
しています。
うまくいかないことがあったら、
寝てしまおう!と対処されている人が
いらっしゃると思いますが、
すごく良い対処です。
成長ホルモンが分泌されるのは、
眠ってから3時間が最大。
体温が下がれば下がるほど、
分泌は増えます。
そこで、
眠る1時間前に、
汗ばむ程度のエクササイズを5分ほど。
ストレッチや簡単な筋トレでも結構です。
翌朝の熟眠感が変わってきます。
Posted by ActiveSleep at
06:40
│Comments(0)
2012年03月27日
掃除は寝室からスタート
さて、掃除でもするか。
とはじめるときは、リビングからはじめる方が
多いと思います。
目に見えているところなので、
重点的に掃除したいですね。
呼吸している空気のことを考えてみると、
リビングと寝室は、同じぐらい呼吸しています。
寝室の空気は、
6~8時間吸い続ける。
熱がこもりやすいので、
カビも生えやすい。
こう考えると、ちょっとコワイですね。
睡眠学会でよく話題に出るのは、
枕カバーです。
あんまり洗っていない・・・
最も顔に近いので、
清潔にしておくことがアレルギー対策にも
重要と言われます。
頻繁には無理でも、
今日は洗ってみようか。
掃除のとき、寝室からはじめてみようか。
そんな行動から、
睡眠はリッチな時間になっていきます。
とはじめるときは、リビングからはじめる方が
多いと思います。
目に見えているところなので、
重点的に掃除したいですね。
呼吸している空気のことを考えてみると、
リビングと寝室は、同じぐらい呼吸しています。
寝室の空気は、
6~8時間吸い続ける。
熱がこもりやすいので、
カビも生えやすい。
こう考えると、ちょっとコワイですね。
睡眠学会でよく話題に出るのは、
枕カバーです。
あんまり洗っていない・・・
最も顔に近いので、
清潔にしておくことがアレルギー対策にも
重要と言われます。
頻繁には無理でも、
今日は洗ってみようか。
掃除のとき、寝室からはじめてみようか。
そんな行動から、
睡眠はリッチな時間になっていきます。
Posted by ActiveSleep at
05:59
│Comments(0)
2012年03月23日
アメを噛んだら睡眠不足?!
ご自分の睡眠が足りているかどうか…
なかなかわからないものです。
睡眠不足のサインは、自分の行動に現れます。
たとえば、
アメを舐めているとき、
最後まで舐めずにすぐに噛んでしまう。
心当たりありませんか?
これも睡眠不足のサインです。
脳は、睡眠が不足すると、
自ら脳を覚醒したり、
眠らせたりする働きを仕掛けます。
私たちは、その仕掛けに沿って
行動します。
顎の筋肉は、
全身の筋肉の中でもかなり強い筋肉です。
この筋肉は、
抗重力筋と呼ばれ、
重力に対抗して体を支える働きを
している筋肉の1つです。
この筋肉が働くと、
セロトニンという物質が増えます。
セロトニンが増えやすいのは、
リズムのある運動。
1秒に2~3回のリズムです。
噛む動作がまさにそれです。
セロトニンが分泌されれば、
脳は覚醒し、気分が安定していきます。
このサインを、
ほっておくと、うっかりミスや事故につながります。
仕事中や運転中に、
いつもなら当然できることを
ミスしてしまう。
取り返しがつかない状態に
なる前に、脳が出しているサインです。
しっかりキャッチして対処しましょう。
対処は15分でも早寝を。
早寝というと、
1~2時間の早寝のイメージが強く、
15分程度だと、つい時間が余ったと
感じてネットやテレビに時間を
使ってしまいがち。
15分でも早寝を積み重ねれば、
慢性的な睡眠不足は、
返済していくことができます。
なかなかわからないものです。
睡眠不足のサインは、自分の行動に現れます。
たとえば、
アメを舐めているとき、
最後まで舐めずにすぐに噛んでしまう。
心当たりありませんか?
これも睡眠不足のサインです。
脳は、睡眠が不足すると、
自ら脳を覚醒したり、
眠らせたりする働きを仕掛けます。
私たちは、その仕掛けに沿って
行動します。
顎の筋肉は、
全身の筋肉の中でもかなり強い筋肉です。
この筋肉は、
抗重力筋と呼ばれ、
重力に対抗して体を支える働きを
している筋肉の1つです。
この筋肉が働くと、
セロトニンという物質が増えます。
セロトニンが増えやすいのは、
リズムのある運動。
1秒に2~3回のリズムです。
噛む動作がまさにそれです。
セロトニンが分泌されれば、
脳は覚醒し、気分が安定していきます。
このサインを、
ほっておくと、うっかりミスや事故につながります。
仕事中や運転中に、
いつもなら当然できることを
ミスしてしまう。
取り返しがつかない状態に
なる前に、脳が出しているサインです。
しっかりキャッチして対処しましょう。
対処は15分でも早寝を。
早寝というと、
1~2時間の早寝のイメージが強く、
15分程度だと、つい時間が余ったと
感じてネットやテレビに時間を
使ってしまいがち。
15分でも早寝を積み重ねれば、
慢性的な睡眠不足は、
返済していくことができます。
Posted by ActiveSleep at
06:16
│Comments(0)
2012年03月22日
脳内の目覚まし時計を使おう
眠る前に「6時に起きる」と唱えると、
その3時間前から、コルチゾールが分泌されて
起きる準備を始めます。
コルチゾールとは、
副腎皮質ホルモンで、
ストレスがかかっているときに
増える特徴があります。
つまり、起きて活動するという
ストレス(この場合いいストレスですが)に対し、
血圧や血糖値を上げて備えようと
働きます。
しかし、このコルチゾール、
急に起こされると、
準備不足の状態から急激に
分泌されるのでかなり脳と体に
負担がかかります。
起きる時間を意識せずに目覚ましをかけるだけだと、
目覚ましが鳴ったとき急激にコルチゾールが分泌され、
かなり不機嫌な朝になるというわけです。
朝、どうも不機嫌になってしまう、とか
なかなか布団から出られないという人は、
眠る前に3回、
「6時に起きる」「6時に起きる」「6時に起きる」
と頭の中で唱えてみましょう。
この方法、自己覚醒法と呼ばれ、
医療機関でも指導されています。
脳には、こんなに便利な目覚まし機能があります。
ぜひ、使いこなしましょう。
その3時間前から、コルチゾールが分泌されて
起きる準備を始めます。
コルチゾールとは、
副腎皮質ホルモンで、
ストレスがかかっているときに
増える特徴があります。
つまり、起きて活動するという
ストレス(この場合いいストレスですが)に対し、
血圧や血糖値を上げて備えようと
働きます。
しかし、このコルチゾール、
急に起こされると、
準備不足の状態から急激に
分泌されるのでかなり脳と体に
負担がかかります。
起きる時間を意識せずに目覚ましをかけるだけだと、
目覚ましが鳴ったとき急激にコルチゾールが分泌され、
かなり不機嫌な朝になるというわけです。
朝、どうも不機嫌になってしまう、とか
なかなか布団から出られないという人は、
眠る前に3回、
「6時に起きる」「6時に起きる」「6時に起きる」
と頭の中で唱えてみましょう。
この方法、自己覚醒法と呼ばれ、
医療機関でも指導されています。
脳には、こんなに便利な目覚まし機能があります。
ぜひ、使いこなしましょう。
Posted by ActiveSleep at
06:22
│Comments(0)
2012年03月21日
午前の眠気は要注意!
ご自分の睡眠は大丈夫かな?と思ったら、
午前中眠気があるかチェックしてみましょう。
ヒトには、生体リズムといって、
頭が働きやすい時間や体が動きやすい時間、
眠りやすい時間が決まっています。
しかし、生活の仕方によって、
このリズムが、前にずれたり、後ろにずれたり、
またメリハリがなくなったりすることがあります。
そこで、リズムのずれを確認してみましょう。
生体リズムでは、
14時と明け方4時に最も強い眠気が起こります。
昼食後の時間に眠くなったり、
徹夜しても明け方にすごく眠くなるのはこのためです。
午前の8~10時ごろは、
本来はもっとも眠くない時間です。
この時間に眠気があったり、
あくびをしてしまうときは、
①リズムが前にずれて、早く目覚め過ぎている
②リズムが後ろにずれて朝起きられない
この2つのどちらかがみられることが多いです。
①は、早朝覚醒と呼ばれます。
年齢を重ねると見れれることが多いです。
19時ごろから眠くなってしまい、
テレビを見ながらうとうとしてしまうことがあります。
そこで20~21時ごろに布団に入り、
2~3時ごろに目覚めてしまいます。
早く目覚め過ぎるので、
布団の中でじっとしていたり、
仕方ないので、庭仕事などしている人が多いです。
これはかなりつらい時間です。
②は、起床困難、または入眠困難と呼ばれます。
若い人に比較的多くみられます。
学校や仕事場では、ぼーっとして眠い、
あくびが出るといった感じですが、
夕方から家に帰ると元気になり、
そこから夜遅くまで勉強や仕事をしたり、
ゲームやネットをして2時ごろに眠り、
朝がすごくつらくなってしまいます。
寝つきが悪い人にも
同じようなずれが見られます。
19時ごろから、
「今日眠れなかったらどうしよう」と
臨戦態勢にはいり、
21時ごろに布団に入ってじっとしますが、
そのまま何時間も寝付けず、
朝方になってようやく眠ると
もう起きなければいけない時間になってしまいます。
これらを、薬を使わずに
解決する方法があります。
これから、少しずつ、
解決方法をご紹介していきます。
午前中眠気があるかチェックしてみましょう。
ヒトには、生体リズムといって、
頭が働きやすい時間や体が動きやすい時間、
眠りやすい時間が決まっています。
しかし、生活の仕方によって、
このリズムが、前にずれたり、後ろにずれたり、
またメリハリがなくなったりすることがあります。
そこで、リズムのずれを確認してみましょう。
生体リズムでは、
14時と明け方4時に最も強い眠気が起こります。
昼食後の時間に眠くなったり、
徹夜しても明け方にすごく眠くなるのはこのためです。
午前の8~10時ごろは、
本来はもっとも眠くない時間です。
この時間に眠気があったり、
あくびをしてしまうときは、
①リズムが前にずれて、早く目覚め過ぎている
②リズムが後ろにずれて朝起きられない
この2つのどちらかがみられることが多いです。
①は、早朝覚醒と呼ばれます。
年齢を重ねると見れれることが多いです。
19時ごろから眠くなってしまい、
テレビを見ながらうとうとしてしまうことがあります。
そこで20~21時ごろに布団に入り、
2~3時ごろに目覚めてしまいます。
早く目覚め過ぎるので、
布団の中でじっとしていたり、
仕方ないので、庭仕事などしている人が多いです。
これはかなりつらい時間です。
②は、起床困難、または入眠困難と呼ばれます。
若い人に比較的多くみられます。
学校や仕事場では、ぼーっとして眠い、
あくびが出るといった感じですが、
夕方から家に帰ると元気になり、
そこから夜遅くまで勉強や仕事をしたり、
ゲームやネットをして2時ごろに眠り、
朝がすごくつらくなってしまいます。
寝つきが悪い人にも
同じようなずれが見られます。
19時ごろから、
「今日眠れなかったらどうしよう」と
臨戦態勢にはいり、
21時ごろに布団に入ってじっとしますが、
そのまま何時間も寝付けず、
朝方になってようやく眠ると
もう起きなければいけない時間になってしまいます。
これらを、薬を使わずに
解決する方法があります。
これから、少しずつ、
解決方法をご紹介していきます。
Posted by ActiveSleep at
06:37
│Comments(0)
2012年03月20日
仰向けはかなりリスク
食事中に急に咳き込んだり、
むせるなと思ったら、
寝ている姿勢を見直してみましょう。
仰向けは、リラックスしたイメージがあります。
仰向けでくつろいでいる人の広告や、
かわいい寝顔の写真などが、そのイメージをつくっています。
しかし、ヒトはもともと脊椎動物。
四足で過ごすのに適した場所に臓器があります。
仰向けになると、重力によって、
臓器の位置は、体内で上か横に流れます。
横隔膜が上方向に流れれば、
肺の容量は当然小さくなりますので、
呼吸の量が少なくなります。
腰やひざの痛みも、
身体が安定しない状態が7~8時間続くからです。
病院でのうつぶせ寝の指導をしますし、
身体に変形がある方は、うつぶせの訓練をします。
動物はうつぶせ寝をします。
ウサギは、腹を出しているときがありますが、
それは、日光で消毒して寄生虫を駆除しているためです。
うつぶせをすると、体が痛いという人もいます。
首を横に向けて、胸の下に低いクッションか
タオルを敷いてみましょう。
片手を肩の横に出し、もう片方の手は
まっすぐ伸ばして下にさげていましょう。
睡眠中、うつぶせでの動き方を体が覚えてくると、
体の痛みも減ってきますよ。
むせるなと思ったら、
寝ている姿勢を見直してみましょう。
仰向けは、リラックスしたイメージがあります。
仰向けでくつろいでいる人の広告や、
かわいい寝顔の写真などが、そのイメージをつくっています。
しかし、ヒトはもともと脊椎動物。
四足で過ごすのに適した場所に臓器があります。
仰向けになると、重力によって、
臓器の位置は、体内で上か横に流れます。
横隔膜が上方向に流れれば、
肺の容量は当然小さくなりますので、
呼吸の量が少なくなります。
腰やひざの痛みも、
身体が安定しない状態が7~8時間続くからです。
病院でのうつぶせ寝の指導をしますし、
身体に変形がある方は、うつぶせの訓練をします。
動物はうつぶせ寝をします。
ウサギは、腹を出しているときがありますが、
それは、日光で消毒して寄生虫を駆除しているためです。
うつぶせをすると、体が痛いという人もいます。
首を横に向けて、胸の下に低いクッションか
タオルを敷いてみましょう。
片手を肩の横に出し、もう片方の手は
まっすぐ伸ばして下にさげていましょう。
睡眠中、うつぶせでの動き方を体が覚えてくると、
体の痛みも減ってきますよ。
Posted by ActiveSleep at
06:53
│Comments(0)
2012年03月19日
噛めば機嫌が良くなる
朝の脳をしっかり覚醒させるには、どうすれば?
そのカギを握るのは、
セロトニン という物質です。
セロトニンは、脳全体に神経の経路を持っており、
脳をしっかり覚醒させます。
さらに、気持ちを安定させる作用があります。
うつ病の人には不足してしまうため、
セロトニンを補う薬物療法が行われます。
このセロトニン、
リズムのある運動で分泌が増える特徴があります。
リズムとは、1秒間に2~3回。
ちょうど、歩いたり、噛んだりする運動です。
朝食は、あえて固めに調理します。
サラダなどの材料を大きめに切り、
パンは固めに焼く。
日常の中で噛む回数を増やすのはなかなか大変です。
大切だとわかっていても、忙しいとつい丸のみのような食べ方に。
そこで、食べ物を固くすることで自然に噛まずにいられないようにします。
朝、出勤してもしばらくは人と話したくない・・・
なんていう場合には、ぜひお試しを。
セロトニンを増やすことができれば、
脳の中では、睡眠のための物質が増え、
ぐっすり眠る準備は、朝から始まっています。
そのカギを握るのは、
セロトニン という物質です。
セロトニンは、脳全体に神経の経路を持っており、
脳をしっかり覚醒させます。
さらに、気持ちを安定させる作用があります。
うつ病の人には不足してしまうため、
セロトニンを補う薬物療法が行われます。
このセロトニン、
リズムのある運動で分泌が増える特徴があります。
リズムとは、1秒間に2~3回。
ちょうど、歩いたり、噛んだりする運動です。
朝食は、あえて固めに調理します。
サラダなどの材料を大きめに切り、
パンは固めに焼く。
日常の中で噛む回数を増やすのはなかなか大変です。
大切だとわかっていても、忙しいとつい丸のみのような食べ方に。
そこで、食べ物を固くすることで自然に噛まずにいられないようにします。
朝、出勤してもしばらくは人と話したくない・・・
なんていう場合には、ぜひお試しを。
セロトニンを増やすことができれば、
脳の中では、睡眠のための物質が増え、
ぐっすり眠る準備は、朝から始まっています。
Posted by ActiveSleep at
07:11
│Comments(0)
2012年03月17日
お腹がいっぱいで眠くなるのではない
ヒトの眠気には、日内変動があります。
もともと脳の働きを守るためのシステムなのです。
最も強い眠気が明け方4時です。
高速道路や医療の事故が最も多い時間帯です。
徹夜したときは、夜中はバリバリ仕事ができても、
この時間になると急に眠くなってきます。
朝4時は、深部体温が最も低い時間帯です。
ヒトは、体温が低くなると眠くなります。
雪山で「寝たら死ぬぞ!」
というのはこのためです。
次いで眠気が強いのは14時。
お腹がいっぱいだと眠くなると思いますが、
実は午後の眠気は、昼食とは無関係です。
昼食を抜いた状態でも、
同じ時間に眠気が起こります。
ヒトには、およそ12時間のリズムがあります。
覚醒させる神経と眠くさせる神経がせめぎ合い、
14時にはちょうど均衡した状態であると考えられています。
さらに、日常はあまり体験しない眠気があります。
2時間おきの眠気です。
単調な状況下では、
2時間おきに脳は眠くなります。
このリズムの力は弱いので、
会話していたり、楽しいことがあると
あっさりかき消されます。
実感できるのは講義中ですね。
このリズムをかき消すには、
30分に1回は笑えるような楽しい講義をするか、
2時間おきにわざと仮眠時間をつくるかです。
面白くない抗議でも、
「はい、今から1分眠ります」
と一斉に眠れば、
理論上はバッチリ学習できるというわけです。
私は、実際、講義の中で1分眠ってもらっています。
「眠りの構造が実感できました!」と
楽しんでいただけています。
もともと脳の働きを守るためのシステムなのです。
最も強い眠気が明け方4時です。
高速道路や医療の事故が最も多い時間帯です。
徹夜したときは、夜中はバリバリ仕事ができても、
この時間になると急に眠くなってきます。
朝4時は、深部体温が最も低い時間帯です。
ヒトは、体温が低くなると眠くなります。
雪山で「寝たら死ぬぞ!」
というのはこのためです。
次いで眠気が強いのは14時。
お腹がいっぱいだと眠くなると思いますが、
実は午後の眠気は、昼食とは無関係です。
昼食を抜いた状態でも、
同じ時間に眠気が起こります。
ヒトには、およそ12時間のリズムがあります。
覚醒させる神経と眠くさせる神経がせめぎ合い、
14時にはちょうど均衡した状態であると考えられています。
さらに、日常はあまり体験しない眠気があります。
2時間おきの眠気です。
単調な状況下では、
2時間おきに脳は眠くなります。
このリズムの力は弱いので、
会話していたり、楽しいことがあると
あっさりかき消されます。
実感できるのは講義中ですね。
このリズムをかき消すには、
30分に1回は笑えるような楽しい講義をするか、
2時間おきにわざと仮眠時間をつくるかです。
面白くない抗議でも、
「はい、今から1分眠ります」
と一斉に眠れば、
理論上はバッチリ学習できるというわけです。
私は、実際、講義の中で1分眠ってもらっています。
「眠りの構造が実感できました!」と
楽しんでいただけています。
Posted by ActiveSleep at
07:11
│Comments(0)



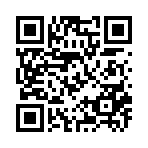

 Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved