2013年08月23日
脳科学という言葉で信頼性が上がってしまう!?
おはようございます。
脳科学的な表現が文章に入ると
情報の質を適正に判断できなくなると。
これは「ジンクピリチオン効果」と命名されています。
言葉の音感と新規性に信頼度が増す。
意味が不明瞭な用語がつくと、
それを聞いた一般の人は信頼度が上がり、
逆にそれを聞いた専門家の信頼度は下がるとのこと。
「ジンクピリチオン配合!」みたいな
フレーズがつくと「おお!なんかすごそう!」という
反応が起こるというものです。
これは
脳科学という用語においても同じような作用がある。
例えば、
「テレビを見ると数学が得意になる。
なぜならテレビを見ているときには
数学と同じ場所の脳の部位が活性化するからだ」
そして脳画像やグラフが並ぶと
「なるほどー」と。
イヤイヤないない(笑)
脳科学という言葉には中身の説明なしに
信頼度を高める作用がある。
このことを知った上で、
情報とうまく付き合っていきたいですね。
脳が画像化されて、2000年以降に
精神疾患は心が弱い人がなるのではなく、
脳の疾患なのだという認識が広まったということは、
とても画期的なことでした。
見えなかったものが見えるようになる。
しかし、見えたことによって、
見えなかったときのような詳細な考察が省かれてしまうのは、
上記のような弊害を生み出す可能性があります。
脳、というと特別な存在な気がしますが、
脳も単なる内臓です。
脳画像を胃カメラの画像と同じような目線で
見ていただくと、
脳が活性化という言葉だけで「なるほど!」とは
思わないと思います。
情報は自分を前進させるためのもので
あってほしいですよね。
「あなたの人生を変える睡眠の法則」
http://www.amazon.co.jp/dp/4426115272
この本は、
脳の働きを高めるために睡眠を活用するという
視点から、脳と睡眠の仕組みを詳しくご紹介しています。
これも脳の情報です。
ただ鵜呑みにするのではなく、
ご自分の生活を前進させることができる情報なのかを
しっかりと吟味して読んでいただけたらうれしいです。
Posted by ActiveSleep at
09:24
│Comments(0)



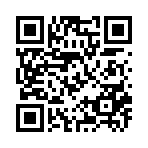

 Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/作業療法士 菅原洋平の生活術 ALL Rights Reserved